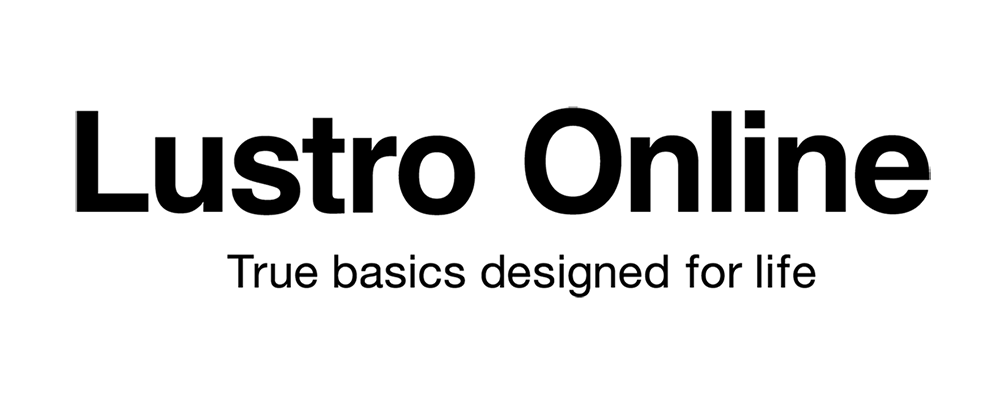2022/08/29 16:33
2. プラスチックが日本に伝来
セルロイドの曲げ加工の製品を製造販売していた岩崎商店ですが、商売は軌道に乗って段々と規模を拡大していきました。
そして、屋号を岩崎商店から合名会社岩崎工業に変更します。
合名会社とは・・個人事業主が複数人いる状態で、共同事業化した状態を想定した会社形態。合名会社を構成する社員は出資をして業務も執行し、企業の所有と経営が一致している。社員は原則として各自が業務を執行し、会社を代表する。(Wikipediaより引用)
とあります。
ですので、その時の実態はあまりよくわかりませんが、岩﨑福松のような自分で製品を作り販売し、会社の経営も見ている人が複数いたのでしょうか。現代の会社では分業制がほとんどですが、当時は多くの仕事を一人でこなすようなやり方が主流だったのでしょうか。もし当時の人がまだご健在なら一度聞いてみたいところです。
1950年後半辺りに海外から入ってきた石油由来のプラスチックという原料が日本でも大量生産され始め、市場にもプラスチック製の商品が出始めます。
これが岩崎工業の転換期の1つとなりました。
1957年には東大阪に会社を移し、縦型の射出成形機を導入してプラスチックの射出成形を始めています。
期を同じくして、日本には大量の横文字の言葉や商品が入ってくることとなります。
そしてそれらの言葉の浸透を更に押し進めたのが、1964年の東京オリンピックです。
コカコーラ、デルモンテ、バヤリンスなどの今では当たり前に聞く横文字の商品はこの頃に入ってきました。

プラスチックもこれらと同様に東京オリンピックを機に市民権を獲得していくこととなります。
戦後、プラスチックの生産量は急速に増え、1950年にはわずかに1万7000トンだった生産量は、1965年には100倍の170万トンにまで急増しました。
如何にプラスチックが日本の中だけでも需要が大きく増えたかが伺えますね。
この拡大を背景として、岩崎工業は会社としての規模を大きくして行き、今の礎を築くこととなります。
次回の投稿では奈良に本社を移すとこからお話ししたいと思います。
Vol.3に続く。